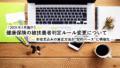はじめに
厚生労働省の労働基準関係法制研究会では、2026年を目途に「14日以上の連続勤務を禁止する」方向で労働基準法改正を検討しています。
これは、過労死防止や健康確保の観点から「一定期間内に必ず休息日を設ける」ことを義務化しようとする動きです。
現行法(労働基準法第35条)では「毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4回以上の休日」を与えればよいため、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合には、最大で22日連続勤務が可能とされています。
例:4週で4日の法定休日を月末にまとめて与える運用の場合
月初から22日間連続勤務しても法令上は違反とはなりません。
つまり、現行法では理論上「22連勤」まで許容されるのが実態です。
このため、「14日を超える連続勤務を禁止する」改正が実現すれば
特に変形労働時間制を運用する企業には大きな影響が出ます。
改正の背景と目的
・長時間労働や過労死リスクの抑制
・変形労働時間制下での“実質的な連勤”是正
・欧州諸国並みの勤務間休息制度に近づける狙い
現行制度では法的には問題がなくても、22日連勤が現実的に健康を損なう水準であるとの指摘がなされています。
中小企業が直面する主な課題
シフトが回らない・代替人員の確保が困難
飲食、宿泊、介護、運輸など、人手が限られる業界では「14日以内に1日の休日を必ず与える」ことが難しくなります。
繁忙期の長期連勤体制が取れず、追加採用や外注コストの増加が避けられません。
勤怠・シフト管理の複雑化
週単位に加えて2週間単位での休日確認が必要になります。
Excelや紙の出勤簿では確認が難しく、勤怠システムの設定変更や導入コストが課題です。
出張・現場型業種での運用負
建設業や製造業などでは、現場単位で連続勤務が発生しやすく、
「途中で休みを取らせる」ために現場調整や宿泊費増加が見込まれます。
名ばかり管理職のリスク拡大
管理職が休日に穴埋め勤務をするケースでは、
実態として労働者とみなされ、是正勧告・残業代請求リスクが増します。
「まとめ休み」運用の見直しが必要
現在、変形労働制で月末に休日をまとめて付与している企業は、
休日の分散付与へ就業規則やシフトを見直す必要があります。
社労士としての支援ポイント(より実務的に)
社会保険労務士は、この改正対応において中小企業を次のように具体的に支援できます。
| 支援内容 | 詳細 |
|---|---|
| ① 勤務実態の「連勤チェック診断」 | 勤怠データをもとに、現状の最長連続勤務日数や休日配置を分析。改正後に違反となる可能性をレポート化。 |
| ② 就業規則・変形労働時間制の見直し | 「休日の与え方」や「変形期間内の休日設定」を14日ルールに合わせて条文化。実際のシフトパターンに即した改定案を作成。 |
| ③ 勤怠システム設定・運用支援 | 利用中の勤怠管理システムで14日連続勤務を自動検知できるよう設定を調整。必要に応じて新システム導入も提案。 |
| ④ シフト運用改善のアドバイス | 業種特性(飲食・介護・運輸など)に応じて、繁忙期・閑散期の勤務配分モデルを提案。休暇の分散付与や交代制運用の導入を支援。 |
| ⑤ 管理職・現場リーダー教育 | 「休日確保義務」や「労務リスク回避」をテーマに、管理職研修を実施。現場での判断ミスを防止。 |
| ⑥ 労基署対策・監査支援 | 改正法施行後の監督指導に備え、労務管理体制の点検や文書整備を実施。是正勧告リスクの低減。 |
✅ ポイント:
単なる就業規則改定だけでなく、「勤務実態の把握」+「シフト・勤怠管理体制」まで一体的に整備することが重要です。
まとめ
現行の変形労働時間制では最大22日連続勤務が可能ですが、
改正後は「14日を超える連続勤務は禁止」となる方向です。
これは従業員の健康確保に資する一方、
中小企業にはシフトや休日運用の見直しが求められます。
早めに勤務実態を洗い出し、休日付与ルールを整備することで、
改正後も安定した運営と法令遵守の両立が可能になります。
貴社の勤務実態診断・就業規則改定は、社会保険労務士にご相談ください。
リンク:及川社会保険労務士事務所_予定されている労働関係の法律改正
リンク:及川社会保険労務士事務所_労働関係法改正に向けた企業・従業員の準備ポイント
リンク:及川社会保険労務士事務所_お問い合わせ