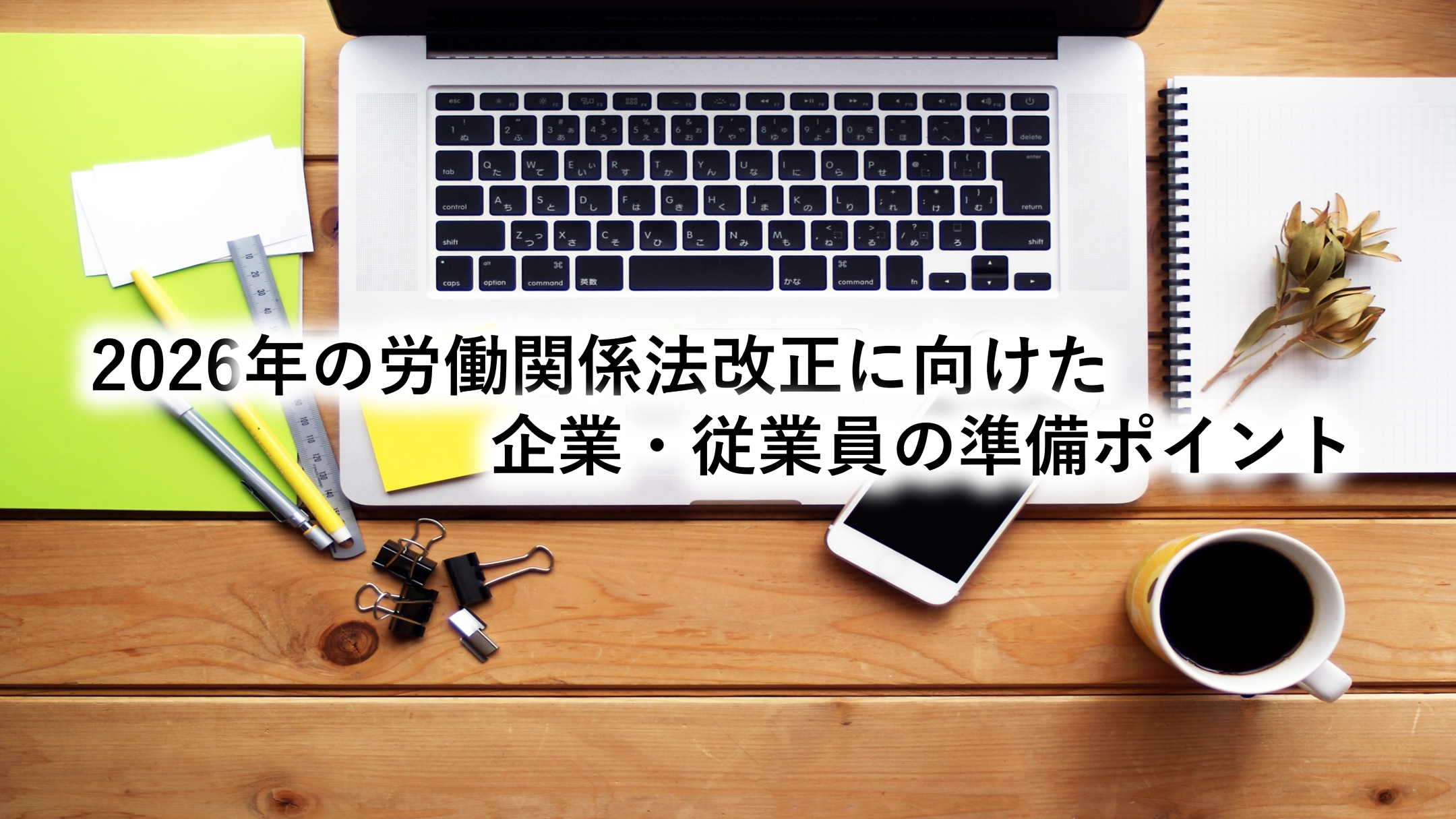はじめに
働き方の多様化、労働者の健康管理や安全衛生への関心の高まりを背景に、厚生労働省では 2025年~2026年を目処に複数の労働関連法制の見直しを進めています。
特に 2026年には、労働基準法・労働安全衛生法などで企業側に求められる義務・対応が強化される可能性があります。
この改正動向を前もって把握し、自社の体制整備に備えることが重要です。

労働基準法(改正検討中)
主な検討論点
厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」からの報告書案などをもとに、現在議論されている主な論点は以下の通りです。
| 論点 | 内容概要 |
|---|---|
| 連続勤務の上限規制 | 14日以上の連続勤務を禁止の可能性! ※現在は理論上最大 48 日連続勤務可能 |
| 法定休日の特定義務化 | 法定休日を明確に指定する義務を企業に課す方向性 |
| 勤務間インターバル制度の義務化 | 労働終了から次の勤務開始までの間隔を一定時間確保する制度を義務付ける案が検討中。 |
| 年次有給休暇取得時の賃金算定見直し | 有給取得時の賃金を「通常賃金方式(所定労働時間に対する賃金)」で払うことを原則化する方向。 |
| 割増賃金の通算見直し(副業・兼業) | 副業・兼業労働者に対して、同一企業に限って労働時間通算が可能とする制度を見直す案。 |
| その他/労働者・事業の定義見直し | 「労働者」と「事業」の定義見直し、テレワーク・みなし労働時間制の取扱いなども検討対象。 |
予想される対応
・勤怠管理システムの改修
・休日日数・休日割り当ての見直し
・有給休暇取得促進体制・賃金処理ルール改定
・就業規則・雇用契約書の見直し
・副業・兼業の労務管理ルール整備
上記のような対応を準備する必要があります。
現在、多くの会社さんでは、法定休日の特定は行わず、「4週を通じて4日の休み」などと規定していることが多いように感じます。
法定休日を特定すると、割増賃金率などで変更が必要になる場合があるので、システムの改修を含めた対応が必要になる可能性があるため、前もっての準備が必要になります。
労働安全衛生法の改正(2026年4月施行中心)
改正の目的と全体像
2025年5月に改正法が公布され、2026年4月1日を中心に順次施行される予定です。
目的は、多様な働き手が安全・安心に働き続けられる環境を整備することとされています。
主な改正ポイント
・個人事業者等も対象に含む安全衛生対策の強化
従来「労働者」を対象にしていた安全衛生義務を、個人事業者等も含む作業従事者混在作業での安全確保義務を事業者に課すようになります。
・ストレスチェック義務化の拡大
50人未満の事業場でもストレスチェックの実施義務化を導入(ただし猶予期間を設けるなど配慮)
・化学物質管理の強化
表示・通知対象物質の追加(2026年4月)
石綿障害予防規則の改正(2026年1月)
新規化学物質の電子申請義務化(2026年7月)
有機溶剤中毒予防規則の見直し(2026年10月)
・機械設備・検査制度の見直し
ボイラー、クレーンなどの設計審査や検査の実施機関拡大、検査基準遵守の義務付け強化など。
・高年齢労働者の災害防止措置強化
年齢に応じた安全対策実施を事業者の努力義務とし、国が指針を公表する。
その他関連法制の改正見通し
以下は、労働基準法・安全衛生法以外で注目すべき改正・見直し動向です。
公益通報者保護法(ホイッスルブロワー法)
2026年中に改正施行が予定されており、通報者保護および通報制度の整備義務化が強化される見込み。
※ホイッスルブロワーとは、日本語で表現すると「内部通報者」となります。
労働施策総合推進法およびハラスメント関連法制
労働政策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の改正により、カスタマーハラスメント・求職者に対するセクシュアルハラスメント防止措置が事業主の義務とされる方向性。
また、従業員数 101 人以上の企業に対し、「男女間賃金差異」や「女性管理職比率」の公表義務を設けるなどの要件拡充が予定されています。
下請法(下請契約法/下請代金支払遅延等防止法)の改正
2026年1月から、下請事業者(中小の請負業者等)の利益保護・公正取引促進のための改正が予定されています。
社会保険・年金制度関連
2026年10月には、パートタイマーが厚生年金に加入するための「年収 106 万円」基準の廃止案が検討されています。これにより、パートタイマーの社会保険加入範囲が拡大し、現状の制度内で雇用保険に加入する人が社会保険に加入する必要がある様に変更になる可能性があります。
企業としての準備ステップ・対応方針
以下は、改正に備えて企業が取るべき検討・準備ステップの方向案です。
- 改正スケジュールの把握と影響範囲の整理
どの法改正がいつから施行されるかをスケジュール化し、影響範囲を洗い出す。 - 就業規則・勤務規程の見直し/整備
連続勤務制限、勤務間インターバル、有給休暇賃金算定ルール、休日規定、兼業規定などを改正案を見据えて修正案を準備する。 - 勤怠管理・労働時間管理システムの改修
新たな勤務上限規制や間隔規定に対応できるようシステム側の改修を検討する。 - 安全衛生体制の強化
ストレスチェック義務化拡大、化学物質管理、機械設備検査体制見直し、高年齢者向け安全対策など、現行制度との差分の対応策を検討・実施。 - 通報制度・ハラスメント対応体制の整備
公益通報制度の強化見込み、ハラスメント防止義務の拡充見通しを踏まえて、通報窓口設計、相談ルート、社内周知・教育を強化。 - 社内教育・意識啓発
管理職・労務担当者に新制度内容を周知し、留意点を整理したマニュアルや研修を準備。 - 社外専門家の活用検討
労働法や安全衛生法に詳しい社会保険労務士、産業医、法務顧問と相談しながら、制度設計を補強。 - 段階的運用テスト・パイロット導入
変更範囲の大きい制度については、小規模部門などで先行運用して問題点を洗い出し、本格導入に備える。
想定リスク・留意点
・法改正内容が最終確定するまでには変更余地があるため、確定版を注視する必要。
・改正後の罰則・違反リスクの増大(例:安全衛生、通報対応)
・中小企業に対する対応負荷(人的リソース・コスト)
・運用実務面での突発的対応(例:連続勤務制限でシフト再編、労働時間超過抑制)従業員・パートタイマー・兼業者との契約関係・関係性見直しリスク
おわりに
2026年を見据えた労働関係法制の見直しは、企業側にとっては「義務強化」への対応が要求される一方、従業員の働きやすさ・健康維持にも資する改善が含まれています。
今から段階的に体制を見直し、運用を試行することで、法改正直後の混乱を最小化できるよう準備を進めておきましょう。
リンク:厚生労働省_労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
リンク:厚生労働省_労働基準関係法制研究会
リンク:及川社会保険労務士事務所_2026年に予定されている労働関係の法律改正