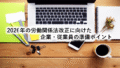「同一労働同一賃金」という言葉は近年よく耳にするようになりました。
言葉の字面から「同じ仕事をしている人がすべて同じ給料をもらう」と勘違いすることが
多いように感じます。
先日も、東京都内のバス会社で、正社員と非正規から登用された正社員の給料待遇差が
問題となり判例が出ましたが、疑問のコメントが多くあったように感じます。
正規社員と非正規社員の関係に適用される場合と、正社員同士に関係する場合とでは、その法的な位置づけや取扱いが異なることで誤解が多い部分でもありますので、整理してみましょう。

正規社員・非正規社員間の同一労働同一賃金
こちらは 「パートタイム・有期雇用労働法」 で定められている内容です。
この法律は、非正規労働者(いわゆるパートタイマーやアルバイト)と正社員の間での賃金や
待遇の不合理な格差を禁じるもので、次の事柄を禁止しています。
【均等待遇】
職務内容や配置変更の範囲が同じなら、正規社員と同じ待遇にしなければならない。
つまり、仕事の内容や異動の有無が正社員と同じ場合
給与金額や福利厚生などの待遇で差をつけることはできない。
【均衡待遇】
給与や待遇に違いがある場合でも、その違いに応じた合理的な差に限定しなければならない。
簡単に解説すると、正社員とパート・アルバイトで給与額や待遇に差がある場合でも
その差に応じてバランスをとる必要がある。
【説明義務】
待遇差がある場合、その理由を求められれば会社は説明しなければならない。
従業員から質問をされた場合、会社がしっかりと説明をする必要があります。
つまり”「正社員と非正規社員で不合理な格差を設けない」”ことが法律で義務づけられています。
正社員間の同一労働同一賃金
一方で、正社員同士の賃金格差については、直接規制する法律は存在しません。
例えば
同じ部署で似たような仕事をしていても
年齢・勤続年数・評価結果などによって賃金差が生じることは法律上問題ありません。
ただし、差別的な取扱い(性別・年齢など不当な理由)や、合理性を欠く極端な差は
裁判で争われる余地があります。
このように、正社員間では差があったとしても、それが差別からくるものでは無ければ
法律上規制する法律は無く、認められるケースも多くあります。
勘違いしやすいポイント
- 「同一労働同一賃金=全員同じ給料」ではない
→ 職務内容や責任範囲が違えば、賃金差は合理的なものとして認められます。 - 正社員同士には法律で義務化されていない
→ パートや契約社員と正社員の関係は法的規制あり。正社員同士は現状では規制なし。 - 説明できる差は認められる
→ 「正社員だから支給・非正規だから不支給」といった一律区分は不合理ですが、
「職務範囲の違い」「責任の重さ」など具体的に説明できる差は認められます。
まとめ
非正規と正規の間は「不合理な格差禁止」が法律で義務化されています。
正社員とパート・アルバイト間の給与や待遇の格差には注意を払わなければなりません。
しかし、正社員同士は、法律上は規制がなく、会社の賃金制度設計や労使合意に
委ねられているのが現実です。最初にあげた、東京都のバス会社での事件のように
正社員と正社員の間では法律の規制が無いため、格差が発生することがあります。
ただし、今後の法改正や社会的要請により、正社員間でも「同一労働同一賃金」のルールが
求められる可能性があります。
当事務所では、企業の実態に合わせた
賃金制度の見直し・就業規則の整備・説明体制の構築 をサポートしております。
お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから!
リンク:厚生労働省_同一労働同一賃金特集ページ
リンク:厚生労働省_同一労働同一賃金ガイドライン
リンク:厚生労働省_パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用改善のために